かまどの由来について
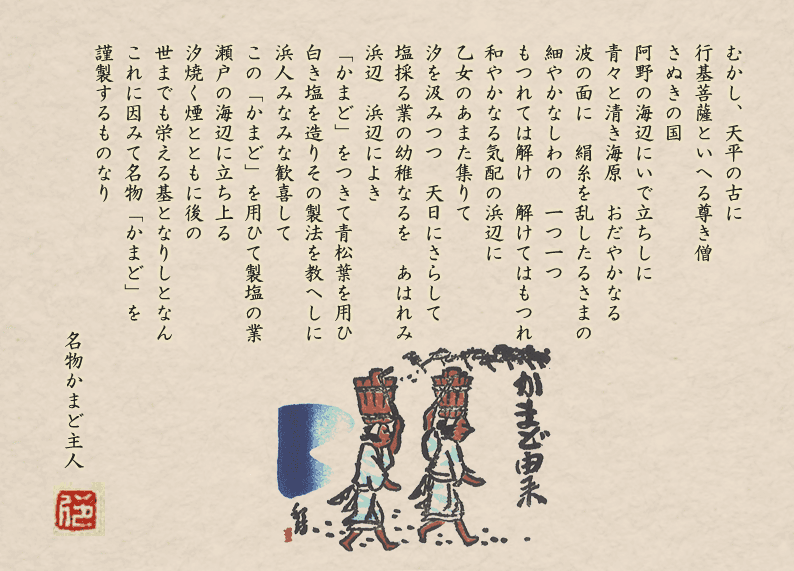
むかし、天平の古に 行基菩薩といへる尊き僧
さぬきの国 阿野の海辺にいで立ちしに
青々と清き海原 おだやかなる 波の面に絹糸を乱したるさまの
細やかなしわの 一つ一つ もつれては解け 解けてはもつれ
和やかなる気配の浜辺に 乙女のあまた集りて
汐を汲みつつ 天日にさらして 塩採る業の幼稚なるを あはれみ
浜辺 浜辺によき 「かまど」をつきて青松葉を用ひ
白き塩を造りその製法を教へしに
浜人みなみな歓喜して この「かまど」を用ひて製塩の業
瀬戸の海辺に立ち上る 汐焼く煙とともに後の
世までも栄える基となりしとなん
これに因みて名物「かまど」を 謹製するものなり
名物かまど主人
【口語訳】
昔、天平時代のこと。
行基菩薩という高僧が、さぬきの国(現在の香川県)の阿野の海辺にやって来ました。
青く澄んだ穏やかな海の水面には、まるで絹糸をほぐしたような、細かく美しい波の線がもつれたりほどけたりして、なんとも穏やかな雰囲気の浜辺でした。
浜辺では、たくさんの若い娘たちが集まり、海水を汲んで天日にさらしながら、一生懸命、慣れない手つきで塩を作っていました。
その姿に心を打たれた行基菩薩は、浜辺のあちこちに「かまど」(釜を据える炉)を築き、青い松葉を燃料に白い塩を作る方法を教えました。
人々は皆とても喜び、「かまど」を使って塩づくりをするようになりました。
その煙はやがて瀬戸内の海辺に立ちのぼり、この塩づくりの技術は後の世にも受け継がれ、地域の繁栄の礎となりました。
この由来にちなみ、「名物かまど」と名付け、心を込めてお作りしています。
名物かまど主人




